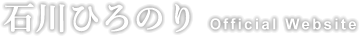石川】次に、教員不祥事の再発防止と信頼回復についてです。
石川】次に、教員不祥事の再発防止と信頼回復についてです。
全国で教職員による不祥事が後を絶ちません。中でも深刻化しているのが、教員による盗撮行為です。公立学校という子どもたちが安心して学ぶ場で、教育を担う教員がこのような卑劣な行為に及ぶことは、教育への信頼を根底から揺るがす重大な問題です。本県でも、本年度に入って既に5件のわいせつ事案による懲戒処分があり、いずれも児童生徒に深刻な影響を与えています。我が会派ではこれまで、代表質問や委員会質疑において、児童生徒への影響と信頼回復の必要性を訴え、外部専門家による研修、大分市を事例に挙げた公的携帯電話の導入、学校環境の見直しなど具体的提案を行ってきました。特に、私的なスマートフォンの持ち込みや使用は、学校現場に構造的なリスクを生じさせると考えています。葉山町や横浜市、名古屋市での盗撮事件を踏まえると、県として市町村ごとのルールや運用状況を正確に把握し、対策の平準化を図る必要があります。
横浜市では、先般の教員不祥事を受け、隠しカメラ探知機器の導入や専門業者による抜き打ち点検、出入口への防犯カメラ増設などの物理的対策に加え、教職員研修、相談体制の整備、児童生徒への心理ケアやアンケート実施などを公表しました。これにより、児童生徒からのSOSの早期発見や相談しやすい関係づくりを促進するとしています。本県では、県教育委員会が臨時の学校長会議を開催するとともに、鍵の管理や年代別不祥事防止研修、啓発チラシの配布、警察OB・NPOとの連携などに取り組んでいます。しかし、再発防止への危機感が高まる中で、県民には「具体的に何が変わったのか」が見えにくく、施策の進捗や効果の発信は十分とは言えません。
今回、知事は定例会見で、学校への信頼回復の重要性や不祥事を起こした場合の影響を「見える化」するなど再発防止の必要性に触れています。令和6年6月の我が会派の代表質問では、公私端末の明確な区別、モデル校での環境整備、学期ごとの児童生徒アンケート実施などを提案しました。それから1年以上経過しましたが、モデル校の環境整備はどの程度進展しているのか、児童生徒や保護者が改善を実感できる状況になっているのか。また、こうした取組みの進捗や成果について、県民に丁寧に説明責任を果たす必要があると考えます。
そこで教育長に伺います。知事のコメントにある「見える化」などの取組みを、県内の教育現場で具体的にどのように示していくのか。また、市町村ごとのルールや運用状況を正確に把握し、教育現場の信頼回復に向けた具体的な取組みが必要と考えますが、所見を伺います。
教育長】次に、教員不祥事の再発防止と信頼回復についてお尋ねがありました。教員の不祥事防止に向けて、モデル校における鍵の適正管理など、様々な取組を進めてきたにもかかわらず、教員による盗撮等の不祥事が相次いでいる現状を、大変重く受け止めています。県教育委員会では、今年度、教員が性犯罪等で逮捕された場合、免許の取上げや退職金の不支給に加え、自分や家族にどれだけの影響があるかを「見える化」するため、元警察官が自らの取調の経験を踏まえて具体的に語る研修動画を作成しました。8月1日に開催した、臨時の県立学校長会議では、全ての教員にこの動画を視聴させるよう指示しましたが、今後、市町村立学校の教員も視聴できるようにして、さらなる啓発を図っていきます。
また県教育委員会では、今年度から新たに、市町村立学校を訪問し、不祥事防止に関して、現場の校長等と意見交換を行う取組みを始めています。そこで得た、不祥事防止に関する市町村毎のルールや運用状況などについて、今後、全ての市町村と共有し、好事例の横展開を図っていきます。こうしたことにより、市町村教育委員会とともに、不祥事防止に全力で取り組み、教育現場の信頼回復につなげてまいります。
石川】昨年6月の代表質問でも、県立学校教職員による逮捕事案が相次いだことを受け、不祥事対策を取り上げた。その際、教育長が全教職員に向け緊急メッセージ動画を発信したと承知している。今回の答弁でも、性犯罪で逮捕された場合の影響を伝える動画を活用するとのことだが、こうした取組みを通じて、教員の意識や行動の変化にどのようにつなげていくのか、そして、その効果をどのように検証していくのか、所見を伺う。
教育長】教員不祥事の再発防止と信頼回復について、お尋ねがありました。逮捕された場合の影響、それから、私からの緊急メッセージなど今後も不祥事防止の取組を総動員することが、教員の意識、行動の変化につながると考えています。こうした取組みの成果を定量的に検証することはなかなか難しいと思いますが、有識者や学校長などから意見を聞いて効果の把握に努めてまいりたいと思います。
石川】今回、市町村毎のルール把握や動画活用による周知徹底が示された。しかし、施策は実施するだけではなく、児童・生徒が安心して学べる環境につながっているかどうか、これを検証することが重要である。再発防止には不断の改善が不可欠であり、成果の見える化と県民への丁寧な説明を重ねながら進めるよう強く求める。