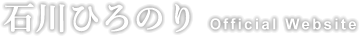石川】次に、生活困窮者対策推進本部の取組みの在り方についてです。
石川】次に、生活困窮者対策推進本部の取組みの在り方についてです。
生活困窮者対策推進本部は、令和3年11月に新型コロナ禍の影響を受けた県民の生活を守るために設置され、子ども食堂支援や進学・就職支援など、経済的に困難を抱える方々を支える施策を進めてきました。現在、物価高騰が続く中で、こうした支援の重要性はさらに高まっています。報道によれば、今年1月以降、値上げされる食品は前年を上回る状態が9か月続き、9月には前年同月比0.6%増の1,422品目となりました。また、11月までに値上げ予定の食品は2万品目を超え、昨年の実績を6割上回っています。今後も賃上げや物流費上昇などで物価高が長期化する可能性が高く、生活困窮者への日常生活に直結する支援の意義はますます大きいと考えます。
しかし、今年7月に報告された令和6年度の取組み実績を見ると、支援の軸が孤独・孤立対策へ移り、従来の暮らしを直接支える施策が弱まっているように感じられます。子ども食堂支援金は支給額が半減し、対象箇所も減少、今年度この事業は廃止となっています。地域で大切な役割を果たす子ども食堂への支援縮小は、困難を抱える家庭への支援の届き方に影響することが懸念されます。さらに、予算委員会等でも指摘している子ども食堂マップには未登録の事業所も多く、必要な家庭に情報が十分届いていない課題もあります。
県は令和6年3月に策定した新かながわグランドデザインにおいて、生活困窮をプロジェクトの一つに位置づけ、多様な担い手と連携した取組みを進めています。 例えば、令和6年度には「かながわつながりネットワーク」を立ち上げ、緩やかにつながる居場所の必要性を示すとともに、ネットカフェでの生活者が約1,300人との実態も明らかにされました。
しかし、何より重要なのは、新たな施策を進める一方で、生活に密着した支援が後退しては本末転倒であるという点です。物価高騰や所得格差の中で切実に求められているのは、生活の基盤を守る、住まいや食、学びなど日常に直結した支援であり、その充実こそが県民の安心につながると考えます。
そこで知事に伺います。物価高騰が続く中、生活に密着した支援の充実が求められていますが、生活困窮者対策推進本部として今後どのように取り組んでいくのか、所見を伺います。
黒岩知事】次に、生活困窮者対策推進本部の取組の在り方についてです。
生活困窮者対策推進本部では、これまで生活困窮当事者や支援に携わるNPO等の意見を伺いながら、困難を抱える子ども・若者や女性、孤独・孤立に陥っている方などへの支援に取り組んできました。具体的には、引き続く物価高騰の中、支援を必要とする子ども食堂へ、企業等からの寄附を適切に分配するためのマッチングの仕組みづくりや、生活に困窮する若者等への大学受験費用の支援などを行ってきました。また、今年度からは、低所得世帯の子どもを支援するため、塾などで使える学習クーポンを配付する市町村事業への補助や、住居不安定者の自立を後押しするため、生活基盤を立ち上げる際に必要となる家具や家電等の購入費用への支援を、新たに開始しました。しかしながら、物価高騰等の影響は未だに大きく、県民の皆様のくらしは、厳しい状況が続いています。生活困窮者対策推進本部では、引き続き、生活に困窮している方々の意見を伺いながら、当事者の目線に立った必要な取組をしっかりと進めてまいります。