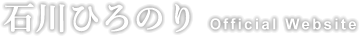石川】次に、外国人受入れ環境の強化と市町村支援についてです。
石川】次に、外国人受入れ環境の強化と市町村支援についてです。
近年、我が国に在留する外国人は急増し、令和6年末時点で約377万人、外国人労働者は同年10月時点で約230万人と過去最高を更新しています。背景には地方の人材不足や国の制度改正がありますが、現場では雇用確保にとどまらず、日本語教育、子どもの就学支援、医療・福祉対応、地域住民との摩擦など、生活者としての外国人に関わる課題が深刻化しています。
例えば、宿泊業では慢性的な人材不足が続き、外国人労働者の活躍は不可欠となっています。その中で、在留資格「技術・人文知識・国際業務」、通称「技人国」を活用し、観光学を学んだ人材がフロント業務や通訳を担うなど、専門性を生かした雇用が広がっています。この資格は高い日本語力を必ずしも必要とせず、母国語や英語を活かして外国人客に対応できる点が利点とされています。さらに家族帯同も認められ、本人だけでなく家族も地域で生活することになり、その結果、外国人住民が急増する市町もあり、教育や医療、福祉など幅広い分野での支援が不可欠となっています。
全国知事会は本年7月、「外国人の受入れと多文化共生社会の実現」に向けた提言を国に行い、制度設計や財源確保、基本法の制定、司令塔組織の設置を求めました。我が会派も市町村の現場の声を伺い、その厳しい状況を強く認識しています。外国人住民の割合が増えれば、学校や保育所は突然の受入れ増に苦慮し、多言語情報提供や生活相談の需要も急増します。小規模自治体では、一人の職員が多分野を兼務し、外国人対応が後手に回ることも少なくありません。文化や生活習慣の違いから摩擦が生じ、地域住民との軋轢が表面化する例も見られます。さらに、市町村や教育・福祉の現場では、外国人労働者を受け入れた企業が十分な言語教育などを行えず、その役割が自治体に委ねられている実態もあります。多言語による案内資料の整備や日本語教育の充実などは、市町村のみでは限界があり、いまや広域行政である県の支援が不可欠です。外国人はもはや一部業種に限られた働き手ではなく、地域社会を構成する住民の一員となっています。受入れ拡充と同時に、生活基盤の整備を計画的かつ着実に進めていかなければ、地域社会の安定や秩序に影響を及ぼしかねません。
そこで知事に伺います。県として外国人受入れの現状をどのように捉えているのか。また、全国知事会の提言を踏まえ、市町村支援を含めた総合的な多文化共生施策をどのように展開していくのか、所見を伺います。
黒岩知事】次に、外国人受入れ環境の強化と市町村支援についてです。 国は、人材の育成・確保を目的に育成就労制度を創設するなど、外国人の受入れを進めており、外国籍県民は年々増加しています。こうした中、市町村によっては、人的、財政的理由から、外国籍県民の増加に受入環境の整備が追い付いていない地域も見られます。全国知事会でも、こうした課題に関し提言したところですが、県としても、外国人の受入環境の整備は自治体任せにせず、国が責任をもって財政措置を行うよう、引き続き要望していきます。また、多くの外国人が暮らす一方、受入環境に課題がある市町村には、県としての支援も必要です。
そこで、外国人労働者向け日本語講座の開催や、日本語ボランティアの養成、日本語教室の開設などで市町村の取組を支援していきます。さらに、外国人の受入れを進めていくためには、民間企業等と協力して幅広な支援を展開することが重要です。県では、「かながわ外国人材/活用支援ステーション」において、民間企業との連携協定に基づき住宅確保の支援につなげたり、「多言語支援センターかながわ」では、生活相談を受けるなど、外国人材への支援を強化していきます。 今後も、市町村や企業等と一体となって、外国籍県民が安心して暮らせるよう取り組んでまいります。