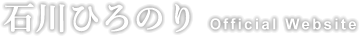石川(裕)委員 次に、漁業の活性化について質問させていただきますけれども、こちらも漁業就業支援事業費ということで、漁業就業円滑化促進支援事業というのがあります。この中でいくと、この目的の中で漁業者の確保が急務だということが書かれています。そういう中で、将来性ある若手就業希望者に対する就業支援を行うことがこの事業の目的だというふうに記載をされています。その上で、この効果は、新規就業者が増加することで県内漁業が活性化し、県民への水産物の安定供給が図られるというのが、その事業の効果ということになっていますけれども、現状について教えてください。
水産課長 現在、令和5年度時点で、本県の漁業就業者数は1,449名となっておりまして、その年齢構成は60歳以上が約44%となって、高齢化が進んでいるという状況です。その中で、県としましても新規就業に取り組んでいるわけですけれども、新規就業者につきましては、令和5年度は39人の新規就業者がありました。それは、前年の令和4年の24人から増加しているという状況です。また、新規就業者の年齢層につきましては、40歳未満が21名、40歳以上が18人という状況です。
石川(裕)委員 そういう中で、県内には県立高校、海洋科学高校、そしてまた吉田島、前は農林って言っていましたけれども吉田島高校、そういう漁業とか に関わる学校がありますけれども、そういう学校と各漁業、林業との連携といいますか、学校側からはどういうような連携をしているのかということを伺いたいと思います。
高校教育課長 まず、海洋科学高校の連携についてですけれども、例えば漁協等で定置網漁のインターンシップなどを実施していたり、そのほかにも地元水産業者の協力を得てインターンシップを実施しており、遊漁船、ノリ養殖、刺し網漁、シラス船引き網漁、タコつぼ漁などの漁業体験を行っております。また、吉田島高校の連携についてですけれども、現在本県の林業の課題解決に向けて、県政総合センター森林保全課や地元企業等と連携したスマート林業の取組等を実施しています。
石川(裕)委員 この学校の中では、そういう漁業、林業、吉田島なんかは演習林を持っているという学校でありますので、そういう連携は取れていると思うんですけれども。本庁として、教育局と漁業の担当の課というんですかね、林業の課というところと、こういう連携をする、ミーティングをするというか、横のつながりと連携の場というのはあるんでしょうか、教育局と。
高校教育課長 進路指導につきましては、各学校のほうで生徒が希望する進路が実現するように支援しているという現状がございますので、連携につきましても、学校がそれぞれ地元の行政の出先機関等とミーティングしているという状況でございます。
石川(裕)委員 今の答弁を踏まえて林業、そして漁業の関わり方、現場の学校と地元がやっているということですけれども、本庁としてやっぱりこういう若手をやっていこうというのだったりとか、やはり
地元の県立高校、せっかくそういう学校があるわけですから、そういうところと連携する必要があると思うんですけれども、それぞれどうでしょうか。
森林再生課長 委員おっしゃるとおり、現場レベルでまずは、この例でいきますと我々でいくと吉田島高校と出先の森林部署との連携というのは、まず第一に考えられることでございます。実際に、まだ事例は少ないですけれども、現場の先ほどの普及員が学校のほうの授業のほうに出向いて、機器の操作の研修といいましょうか補助といいましょうか、そういう取組は実際に行われております。それと、吉田島高校で演習林の学習といいましょうか、久々に演習林を活性化するという要件の中で、いろんな作業を始めるということを取りまとめた発表会を国レベルで行ったときには、その発表の場として、県政センターが仲立してそういう取組を発表したというようなことにつなげたということもございます。今後は、それらの取組を進めた上で、できれば高校卒業した方が、例えば県内の林業系のところに就職するというようなところが望ましいのかなというふうには思っておりますので、まずはそういう教育部門からの連携も、今後はもう少し強めていくようなことも必要かなというふうに思っております。
水産課長 水産行政の側といたしましては、漁業の就業を希望する若者を対象に漁業就業セミナーというものを行っています。これ令和5年度までは、一般を対象にして横浜で行っていましたが、令和6年度からは、年に2回行っています。そのうちの1回は海洋科学高校、1回目は三崎の魚市場、これ三崎のほうに日本さかな専門学校というのができていますので、そちらをメインの対象とした形で行っております。
また、そのセミナーの後に、直接漁業者と学生が対話をするマッチングの場というのを設けております。それから、先ほど教育から話にもありましたインターンシップなどで漁業に関心がある若者ということで、水産技術センターに来ていただいて、調査ですとかそれから魚を飼っているところですね、そういったものを実習していただくということを取り組んでおります。それから、また海洋科学高校で栽培漁業の取組を行っているということに関しましても、水産技術センターのほうで親貝の飼育ですとか、そういったことを技術的な支援をしているという状況でございます。
石川(裕)委員 せっかく、地元にそういうすばらしい学校がありますから、若手の就業というところも中でいけば、そういう学校としっかりと連携をしていただきたいということでこういう質問をさせてい
ただきました。私の質問を終わります。