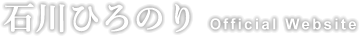作山議員】県は人口減少時代に入っている中、一人あたりの水使用量は減少傾向にあり、料金収入にも影響している。水需要の縮小が進む中、老朽施設の更新を進める財源の確保や、施設の稼働率低下への対応も課題である。このように、人口減少と有収水量の減少という異なる要因に同時に向き合いながら、水道事業は地域の実情に即した柔軟かつ持続可能な整備体制の構築が求められている。そこで、県営水道における膨大な水道管の管理や整備を今後どのように進めて行くのか、所見を伺う。
作山議員】県は人口減少時代に入っている中、一人あたりの水使用量は減少傾向にあり、料金収入にも影響している。水需要の縮小が進む中、老朽施設の更新を進める財源の確保や、施設の稼働率低下への対応も課題である。このように、人口減少と有収水量の減少という異なる要因に同時に向き合いながら、水道事業は地域の実情に即した柔軟かつ持続可能な整備体制の構築が求められている。そこで、県営水道における膨大な水道管の管理や整備を今後どのように進めて行くのか、所見を伺う。
企業庁長】企業庁関係の御質問にお答えします。県営水道における管路整備の取組みについてお尋ねがありました。今年4月に京都市で発生した漏水事故を受け、企業庁では、国からの要請に基づき緊急輸送道路に埋設されている鋳鉄管の緊急調査を行いました。今回の調査では異常がないことを確認しましたが、県営水道の給水区域に張り巡らされた膨大な量の水道管の漏水事故を未然に防止するためには、管路の更新と併せて、日ごろからの維持管理が重要です。そこで、2年ごとに全ての管路の漏水調査を行い、漏水の早期発見に繋げるなど、適切な維持管理に努めています。また、企業庁では、経営計画に基づき、断水の影響が広範囲に及ぶ基幹管路や災害協力病院などの重要給水施設への供給管路等を優先的に更新・耐震化する「戦略的な管路整備」に取り組んでいます。この管路整備に併せて、水需要の減少が見込まれる地域では、水道管の口径の縮小や、管路の集約など、将来を見据えた施設規模の適正化にも取り組みます。
企業庁では、こうした「戦略的な管路整備」などを着実に進めるため、今年2月に「県営水道出先組織再編計画」を策定し、営業所を統合して職員と業務を集約するなど、組織体制も強化していきます。さらに、今月、国が発表した「第1次国土強靭化実施中期計画」の推進施策の一つに、「上下水道施設の戦略的維持管理・更新」が位置付けられましたので、今後の動向を注視し、国庫補助の活用についても検討してまいります。
作山議員】本県において、水道事業の環境は、より一層厳しさを増しています。将来を見据えた戦略的かつ持続可能な整備が重要です。企業庁におかれましては、県民が安心して水を使い続けられるよう、計画的な管路整備を力強く推進していただくことを強く要望いたします。